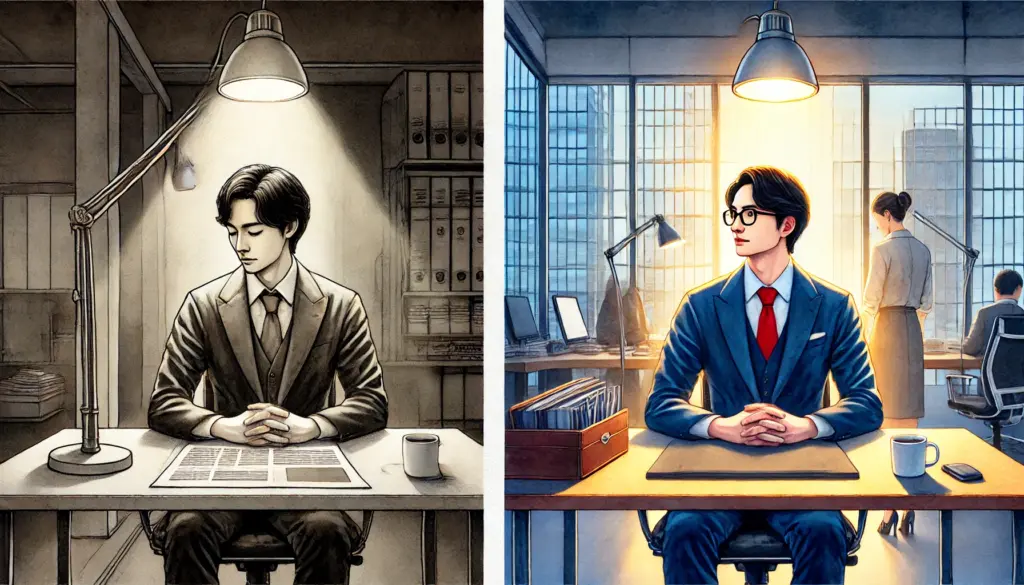
「社労士の年収は本音」で検索している方の多くは、「資格を取れば高収入」というイメージと、実際の雇われ社労士の年収とのギャップに不安や疑問を感じているのではないでしょうか。実際、年収の現実は決して楽観的とは言えず、知恵袋などでは「やめとけ」「悲惨」といった声も目立ちます。また、食えないとのブログ記事も多く見られ、これから資格取得を目指す人にとって不安をあおる情報も少なくありません。
この記事では、社労士という職業の実態に迫り、勤務・開業それぞれの年収の傾向や、平均と年収中央値の違いにも触れながら、現実的な収入水準を解説します。また、社労士試験の難易度や受験資格のハードル、求人市場での評価といった観点からも、「やめとけ」と言われる背景を多角的に検証します。これから社労士を目指す方にとって、キャリア選択の判断材料となるよう、できるだけ本音でまとめています。
記事のポイント
- 社労士の年収が資格の難易度に見合わない現実
- 勤務社労士と開業社労士の収入の違い
- 「やめとけ」「悲惨」と言われる理由の具体例
- 年収中央値や求人情報から見える待遇の実態
社労士の年収は本音でどうなのか?

- 雇われ社労士の年収の実態とは
- 年収の現実は資格に見合うのか
- 「やめとけ」と言われる理由とは
- 「悲惨」との声が出る背景を解説
- やめとけは知恵袋でも話題に
雇われ社労士の年収の実態とは
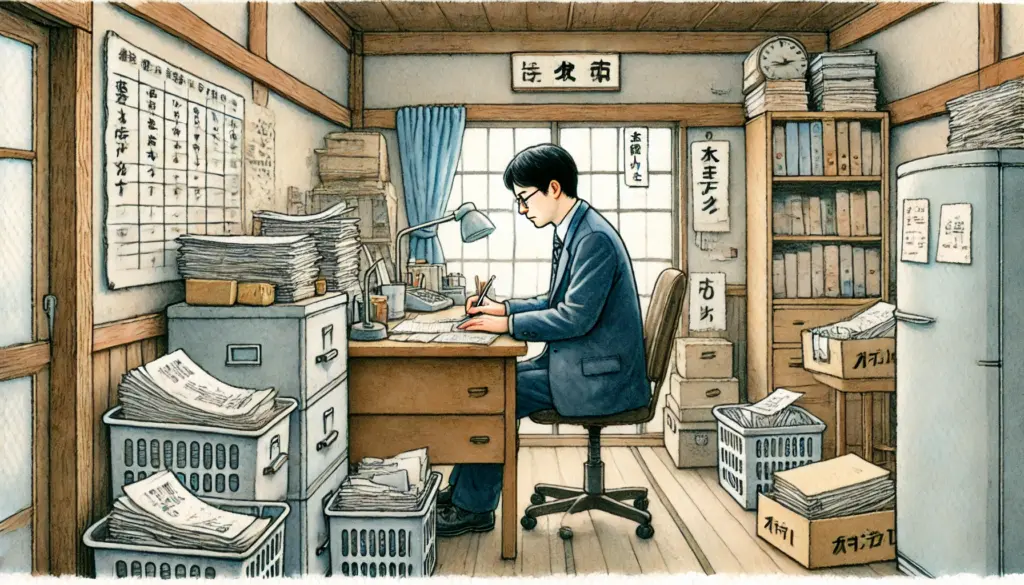
雇われ社労士、つまり企業や社労士事務所などに勤務している社会保険労務士の年収は、一般的に安定している反面、大幅な年収アップは期待しにくいという特徴があります。多くの人が想像するような「資格を取れば高収入」というイメージとは異なる現実があるのです。
例えば、2024年度の社労士実態調査では、勤務社労士の平均年収は約606万円、中央値は500万円と報告されています。中央値が平均を下回っていることから、収入に大きな差があることがわかります。つまり、ごく一部の高年収者が平均を押し上げている一方、多くの社労士は500万円前後の収入にとどまっているということです。
勤務社労士の収入は、主に雇用されている企業の規模や地域によって左右されます。例えば、従業員数1,000人以上の大企業に勤めている場合、比較的高い給与水準が期待できるものの、中小企業や地方の事務所では年収が300万円台にとどまることもあります。
また、経験年数や職位によっても年収は変動します。若手社員のうちは年収が低く抑えられ、年齢や経験が上がるにつれて少しずつ昇給していくという仕組みが一般的です。ただし、大幅な昇給は難しく、昇進して管理職になるか、専門性を活かした役職に就くことでようやく年収600万円〜700万円に届くケースが多いようです。
このように、雇われ社労士の年収にはある程度の安定性がありますが、「資格を取れば一気に高収入」といった期待を持っていると、現実とのギャップに戸惑うかもしれません。慎重にキャリアプランを描くことが重要です。
年収の現実は資格に見合うのか
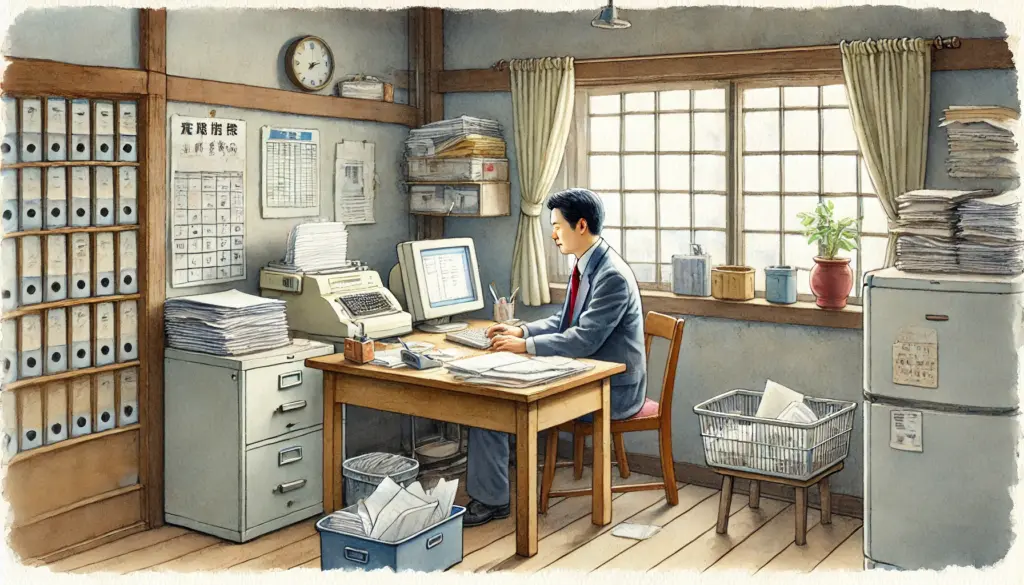
社会保険労務士という資格は、国家試験の中でも難関に位置づけられており、合格率は例年6〜8%前後と非常に低い水準です。受験にあたっては、1,000時間以上の学習が必要とも言われています。しかし、このような高いハードルを乗り越えても、年収がその努力に比例するとは限らないのが現状です。
前述の通り、勤務社労士の年収は平均で600万円程度、開業しても平均売上が1,600万円を超える一方で、実際の所得は経費を差し引くとかなり下がる場合があります。売上の中央値は550万円とされており、資格取得のために費やした時間や費用を考えると、必ずしも「見合っている」とは言えないでしょう。
特に、開業社労士として独立した場合、顧客獲得のための営業活動、競合との差別化、サービス品質の向上など、資格以外のスキルも強く求められます。資格そのものが収入を保証してくれるわけではなく、実務能力やビジネスセンス、さらには市場の需要といった外部要因にも大きく左右されます。
また、厚生労働省の統計では、社労士の平均年収が他の士業(弁護士、公認会計士、税理士など)に比べてやや低めであることも指摘されています。資格の難易度や専門性の高さに比べ、実際の収入が期待ほどではないという声が多いのも、この点に起因していると考えられます。
このように、社労士資格は非常に価値のある専門資格ではありますが、それだけで収入が飛躍的に伸びるとは限りません。資格取得後も継続的な学習と努力、戦略的なキャリア構築が求められるのが現実です。
「やめとけ」と言われる理由とは
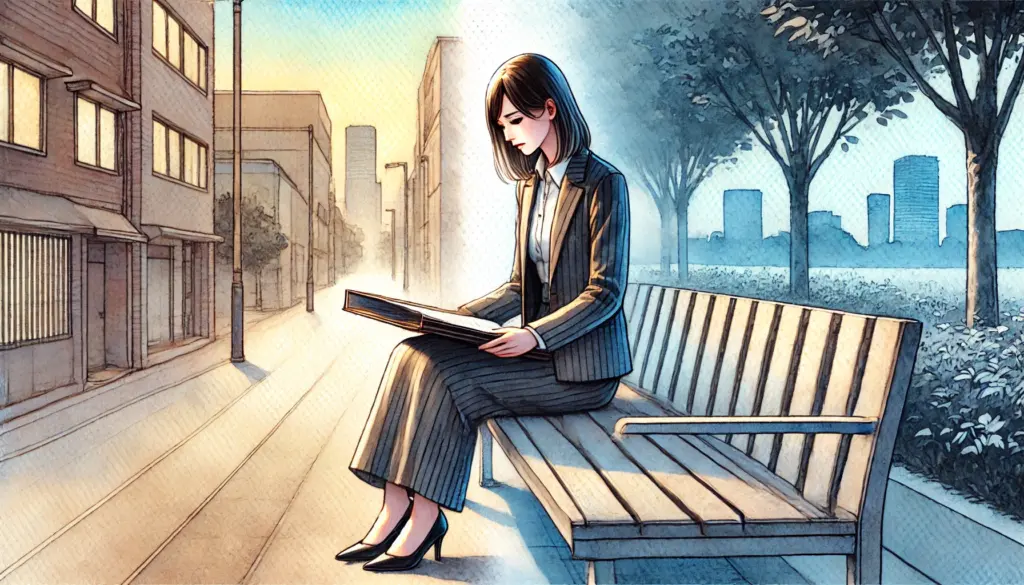
「社労士はやめとけ」といったネガティブな声は、インターネット上の知恵袋や口コミ、ブログなどでも頻繁に見受けられます。その背景には、資格取得にかかる労力と、それに見合わない収入、業務内容の実態など、いくつかの理由が存在します。
まず挙げられるのが、前述のように年収が期待よりも低いという点です。特に勤務社労士の場合は年収が安定しているものの、大きな昇給が見込めず、長く働いても頭打ちになりやすい傾向があります。このため、「割に合わない」と感じる人が少なくありません。
また、業務の内容も「思っていたのと違う」と感じるケースがあります。社労士の業務は、労働保険や社会保険の手続き、帳簿作成といった定型的で事務的な業務が中心です。これらは責任が重くミスが許されないにもかかわらず、地味な作業が多く、やりがいを感じにくいと感じる人もいます。
さらに、開業社労士に関しては、「営業ができないと食っていけない」という厳しい現実があります。資格を取っても、顧客がいなければ収入はゼロ。実際に、開業初年度の売上がほとんどなかったという話も珍しくありません。こうした事例が「やめとけ」という意見の根拠となっているのです。
最後に、法改正が頻繁に行われる分野であるため、常に最新情報をキャッチアップし続けなければならないというプレッシャーもあります。学び続ける姿勢がないと通用しない世界であり、その点も人によっては負担に感じられるでしょう。
このような理由から、「社労士を目指すのは慎重に考えたほうがいい」という警告が発せられているのです。ただし、それはあくまで一部の側面であり、適性と努力次第でやりがいと収入の両立を図ることも可能です。目指す前に、自分に合った働き方や将来像をしっかり見極めることが大切です。
「悲惨」との声が出る背景を解説

社労士の仕事に対して「悲惨」という表現が使われる背景には、収入面や業務内容、人間関係など、さまざまな課題が絡み合っています。特に資格取得の難しさと、実際の働き方・待遇とのギャップが、多くの人にとって失望につながっているようです。
まず、収入に関する落差が一因として挙げられます。社労士試験は合格率が10%未満と非常に厳しい国家資格であるにもかかわらず、資格取得後の初任給や勤務社労士の平均年収は、一般企業の総合職と大差がありません。それどころか、勤続年数が短い若手の間では年収300万円台にとどまることもあります。努力に見合った報酬が得られにくいと感じれば、「悲惨」との印象を抱くのも無理はありません。
次に、業務の実態です。社労士は、労働・社会保険に関する手続きや帳簿作成など、定型的かつ細かい業務を数多く担当します。業務内容自体は専門的ではあるものの、事務作業の色合いが強く、達成感や自己成長を実感しにくいという声もあります。また、繁忙期には過重労働になりやすく、精神的な負担が大きくなることもあります。
さらに、開業した場合でも、すぐに安定した収入が得られるわけではありません。営業活動や人脈構築、価格競争など、社労士の専門知識とは別に、経営者としての資質が問われる場面が多くなります。「資格を取れば食べていける」と思って開業したものの、顧客がまったく集まらず、赤字続きで廃業を検討するケースも少なくないのです。
このように、資格取得の大変さに対して報酬ややりがいが伴わないと感じる人が多いことが、「悲惨」という言葉での表現につながっています。ただし、すべての社労士が悲惨な状況にあるわけではありません。自分に合った働き方を選び、専門性を高めていけば、やりがいのあるキャリアを築くことも十分に可能です。
やめとけは知恵袋でも話題に
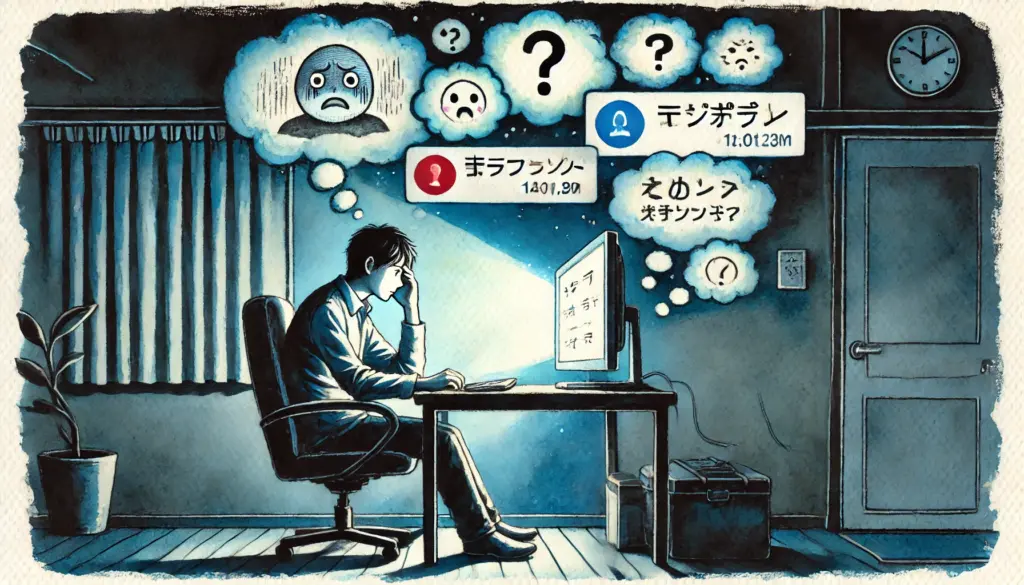
「社労士はやめとけ」というネガティブな意見は、Yahoo!知恵袋や5ちゃんねるといったネット掲示板でも繰り返し取り上げられています。こうした発言が目立つ理由は、社労士を目指す人の期待値と、実際の仕事の内容・待遇とのギャップが大きいことにあります。
インターネット上では、「勉強時間に対して見返りが少ない」「資格を取っても食べていけない」「独立しても顧客が取れない」といった投稿が数多く見られます。これらの意見は決して根拠のないものではなく、実際に資格取得後に苦労している人たちの声が反映されたものです。
特に知恵袋では、「社労士になったけれど後悔している」「転職の幅が思ったより狭い」など、現職の人や資格取得者によるリアルな体験談が寄せられています。匿名での投稿ということもあり、実際の声としては信ぴょう性が高いと受け取る人も多いようです。
一方で、やめとけという意見ばかりが目立つことで、「社労士=失敗する資格」という誤解が生まれている面もあります。知恵袋のような場所には、悩みや不満を抱える人が相談を目的として集まる傾向があるため、ポジティブな成功例が投稿される機会は相対的に少なくなりがちです。
つまり、「やめとけ」と言われているからといって、必ずしもすべての人にとって向いていない職業だとは限りません。むしろ、自分にとって本当に目指す価値があるかどうかを見極めるための参考材料として、こうした声を冷静に受け止める姿勢が重要です。
繰り返しますが、資格取得はゴールではなくスタートです。キャリアをどう築くかによって、得られる結果は大きく異なります。ネガティブな意見を見たときは、それをそのまま鵜呑みにするのではなく、自分の将来像と照らし合わせながら考えることが大切です。
社労士の年収は本音で語れるか?
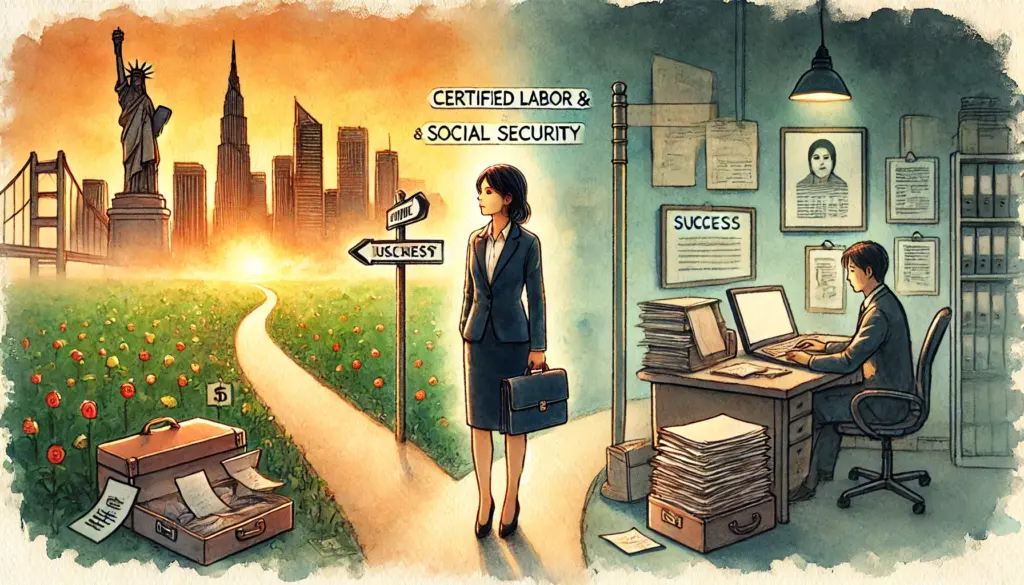
- 「食えないとのブログ」は本当か
- 年収 中央値が示す現実とは
- 難易度と収入が釣り合わない?
- 受験資格と将来性のギャップ
- 求人情報から見える待遇の差
「食えないとのブログ」は本当か

インターネット上では、「社労士は食えない」と断言するブログ記事を見かけることがあります。こうした主張が目立つのには、社労士の働き方や収入構造に関する誤解や、個人の経験が強く反映されているケースが少なくありません。
まず、社労士には「開業型」と「勤務型」の2つの働き方があり、収入の安定性や水準に違いがあります。開業社労士の場合、事務所を構え顧客から直接報酬を得るビジネスモデルであるため、営業力や人脈、サービスの差別化が不可欠です。その一方で、営業がうまくいかずに顧客がつかず、「売上ゼロ」という開業初年度を経験する人も存在します。こういったケースでは、実際に「食えない」と感じるのも無理はありません。
また、ブログに書かれる情報の多くは個人の体験や主観に基づいていることが多いため、すべての社労士に当てはまるとは限りません。「知識はあったが営業ができなかった」「特化分野を持たず、他と差別化できなかった」といった背景があるにもかかわらず、職業そのものが食えないと断じてしまうのはやや極端です。
一方で、うまく経営戦略を立て、継続的に顧問契約を獲得している開業社労士の中には、年収1,000万円を超える人も存在します。つまり、「食えないかどうか」は資格の有無よりも、どのように活用するかにかかっていると言えるでしょう。
このように、「食えないとのブログ」は一部の現実を反映しているものの、それが社労士全体の姿ではありません。情報を読み取る際は、その筆者の立場や背景、成功例・失敗例のバランスを意識することが大切です。
年収 中央値が示す現実とは

社労士の収入について語るとき、平均年収だけを見ると実態を見誤る恐れがあります。そこで注目すべきなのが「年収の中央値」です。これは、すべての収入データを昇順に並べたときに中央に位置する値であり、収入分布の偏りを把握するのに非常に有効な指標です。
2024年度の社労士実態調査によると、勤務社労士の年収中央値は500万円とされています。一方、平均年収は606万円です。ここで注目すべきは、中央値が平均よりも大きく下回っている点です。これは、高収入の一部の人が平均値を押し上げている一方で、大多数は500万円以下の年収に集中している可能性があることを示唆しています。
この分布を見ると、「資格を取ればみんな600万円以上稼げる」という印象は誤解であることがわかります。実際には、年収300万円〜600万円の範囲に多くの社労士が集中しており、特に若手や地方勤務の社労士では300万円台というケースも珍しくありません。
また、開業社労士についても、年間売上の中央値は550万円と報告されています。これはあくまで「売上」であって、そこから事務所運営に必要な経費を差し引く必要があります。その結果、実際の手取り年収はさらに下がることが多いのです。
このように、中央値は現実に近い収入層を把握するうえで非常に参考になります。平均だけでなく中央値にも目を向けることで、社労士として働くことの経済的な実態をより正確に理解できるでしょう。
難易度と収入が釣り合わない?
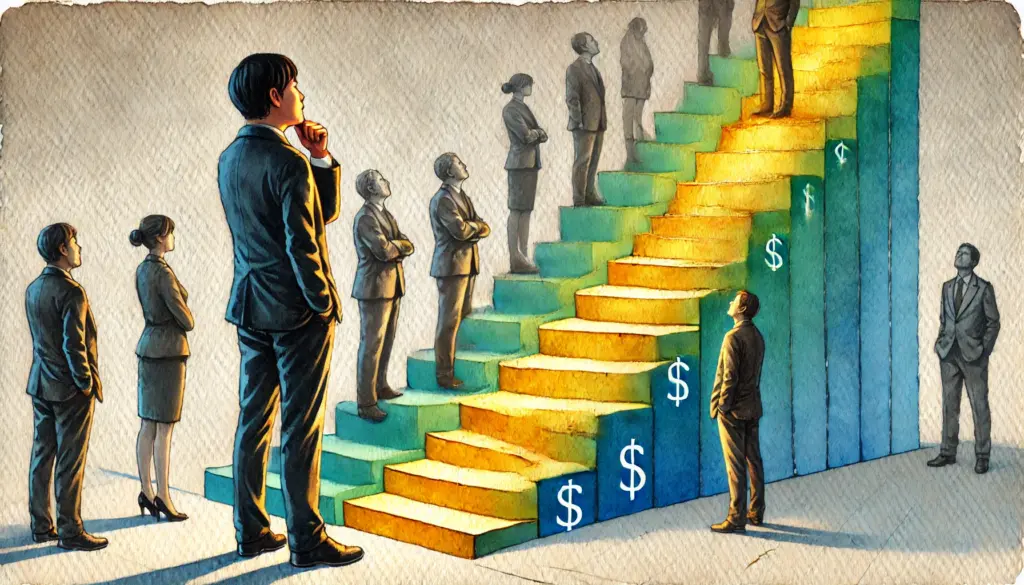
社労士の国家試験は、合格率が例年6%から8%程度にとどまる難関試験として知られています。試験範囲は広く、労働法、社会保険法、年金、雇用、労務管理など、多岐にわたる法律知識が求められます。合格のために必要とされる学習時間は、1,000時間以上とも言われており、受験生にとってはかなりの覚悟が必要です。
これほどの難関を突破しても、その後の収入が期待ほどではないという事実に直面する人も少なくありません。特に勤務社労士の場合、資格手当がつくとしても、その金額は月数万円程度にとどまることが多く、基本給自体は一般事務職や他の管理部門職と大きく変わらないケースがあります。
さらに、開業を選んだとしても、収入の高さは保証されていません。開業には顧客獲得の努力が欠かせず、仮に売上が伸びても、事務所の家賃、人件費、広告費などの経費がかさむと、手元に残るお金は思ったより少なくなる可能性もあります。
このような状況を見て、「これだけ難しい試験を突破したのに、この収入では見合わない」と感じる人が多いのも無理はありません。ただし、収入がすぐに上がらないという現実がある一方で、実務経験を積み、専門分野を確立すれば高収入を実現できる可能性もあります。例えば、助成金申請や人事制度のコンサルティングなど、高度な専門性が必要な分野では、高額な報酬が得られることもあるのです。
つまり、社労士の収入は資格の難易度だけで決まるものではなく、その後の行動と戦略に強く依存します。難易度と収入が釣り合わないという印象は一部事実を反映していますが、それが全体像ではないという点を理解しておく必要があります。
受験資格と将来性のギャップ
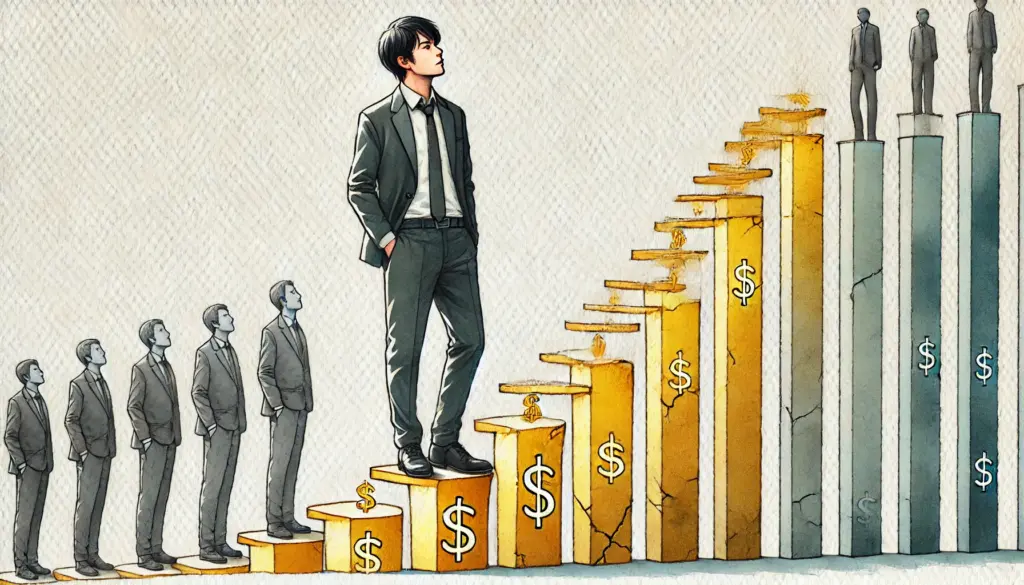
社会保険労務士(社労士)になるには、一定の受験資格が必要です。大学・短大・専門学校卒業、または実務経験があることが条件となり、誰でも気軽に受けられる資格ではありません。さらに、国家試験の合格率は6〜8%程度と非常に低く、長時間の学習と準備が求められます。多くの受験生が何年もかけて合格を目指す、ハードルの高い資格です。
このような背景から、社労士資格には「取得できれば一生食いっぱぐれない」という期待を抱く人もいます。しかし、実際のところ、資格取得後に待っているキャリアや待遇が、その努力と時間に見合っているかどうかについては意見が分かれます。
たとえば、資格を取ったからといってすぐに高収入が得られるわけではありません。勤務社労士として企業や事務所に就職した場合、初任給や年収は300万円台からスタートすることが多く、決して楽に生活できる水準とは言えません。さらに、実務経験のない新人社労士が企業に即戦力として採用されるのは簡単ではなく、「せっかく資格を取ったのに仕事が見つからない」といった悩みも聞かれます。
また、将来的に独立を考える場合でも、すぐに安定収入が得られるわけではありません。営業力や人脈の有無、業務の幅広さが問われるため、資格さえあれば成功できるという単純な構図ではないのです。
こうした現実を踏まえると、受験資格の厳しさや合格の困難さに対して、資格取得後の将来像が不透明であることがギャップとして感じられるのも無理はありません。これから社労士を目指す場合は、資格取得後のビジョンを明確にし、実務経験や専門性の習得、さらには開業やキャリアアップのための準備までを見越して行動することが重要です。
求人情報から見える待遇の差
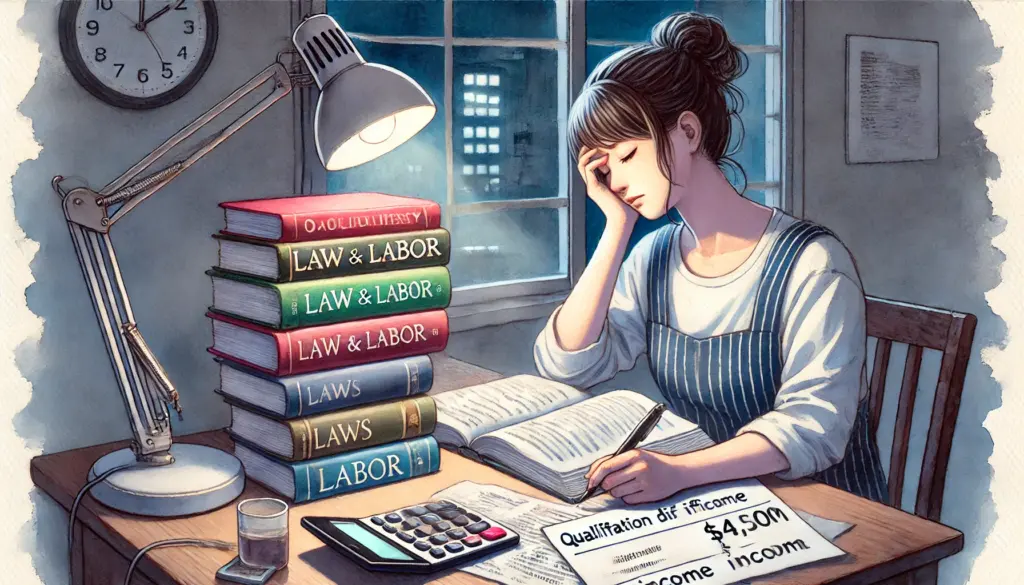
社労士に関連する求人情報を見ると、その待遇には大きな幅があることがわかります。これは、社労士としての働き方や経験、勤務先の規模・地域によって、収入や福利厚生の内容が大きく異なるためです。
まず、企業内で人事・労務部門の一員として社労士資格を活かす求人では、年収400万円〜600万円程度のものが中心です。中には資格手当がつくものの、手当の額は月に1〜3万円程度と限定的で、劇的な年収アップにつながるわけではありません。また、必ずしも社労士資格者を「専門職」として優遇しているわけではなく、あくまで事務職の延長として扱われているケースもあります。
一方、社労士事務所や特定社労士として働く場合、実務経験が重視される傾向にあります。実務経験3年以上を条件にしている求人も多く、未経験者がすぐに高待遇で採用されることは稀です。給与面でも、年収300万円台のスタートが一般的で、昇給には時間がかかることが多いです。
さらに、同じような職務内容でも、勤務地によって年収水準が大きく異なります。首都圏では比較的高めの水準が提示されることが多いですが、地方では年収が100万円以上下がるケースも珍しくありません。これは、地域の物価水準や企業の支払い能力、業務量の違いが影響しています。
こうして求人情報を見比べると、社労士資格の価値が一律ではなく、働き方や勤務条件によって評価のされ方が大きく変わることがわかります。資格を活かして安定した収入ややりがいのある仕事に就くためには、待遇だけでなく、自分がどのようなキャリアを描きたいかを明確にし、それに合った職場を慎重に選ぶ姿勢が必要です。
社労士の年収は本音でどう語れるのか?現実を総まとめ
- 勤務社労士の平均年収は約606万円だが、中央値は500万円と差がある
- 資格を取れば高収入というイメージとはギャップがある
- 企業規模や勤務地により年収が300万円台にとどまる場合もある
- 昇給は緩やかで、管理職や専門職に就かないと頭打ちになる
- 合格率6〜8%の難関資格だが、収入はそれに見合わないこともある
- 経験や実務スキルが収入アップに直結する傾向がある
- 資格手当は月数万円で、劇的な年収アップにはつながらない
- 開業社労士の売上は中央値550万円で、実質所得はさらに低い
- 開業には営業力・人脈・差別化戦略が求められる
- 「やめとけ」「悲惨」と言われる背景には現実とのギャップがある
- ブログやネット上のネガティブ意見は一部の事例に偏っている
- 若手や未経験者は転職や採用面で不利になることがある
- 地方勤務では首都圏より年収が100万円以上低くなることもある
- 労働・社会保険手続きなど地味で事務的な業務が中心
- 資格取得後のキャリア戦略次第で収入とやりがいを両立できる可能性がある